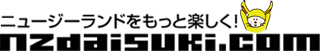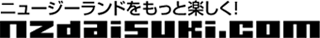皆さんは、「ホームスクール」とか「フリースクール」という言葉を耳にしたことがありますか?。しばらく前までは、あまりなじみのない言葉でしたよね。教育というと、真っ先に浮かぶのは誰もがイメージするような「普通の学校」であり、せいぜい学校の種類で言えば、公立、私立、インターナショナル・スクールくらいでしょうか?。長い間、学校にとって「変革」や「多様化」といったものは無縁のものだったと思います。ところが、教育、学校もこれらの単語から逃れることが出来ない時代になったようです。
ホームスクールもフリースクールも、明確な定義がある訳ではないようです。一般的にはホームスクールが、普通の全日制学校には行かず、家庭や地域で子供の学習の面倒を見る、ということになろうかと思います。親との距離が近くなりすぎるのではないかという危惧は感じますが、特に地域で運営されるホームスクールであれば、閉鎖的な社会である普通の学校よりもかえって広い世界の大人と接することが出来るので、人格形成上はむしろ良いのではないか、という意見もあるようです。それに対してフリースクールは、日本でいう学習指導要領にとらわれず、多様な教育内容を提供する教育機関、ということが言えるようです。正規の学校としての認可は受けられないのが一般的ですが、一定の要件を満たせば進学や就職も可能なようです。また、認定試験をパスすれば卒業資格を得ることが出来ます。
何らかの理由で不登校になってしまった子供に複数の選択肢があることは良いことだと思います。例えば日本の学習指導要領に沿った内容は受けたくない、もっと別の勉強がしたいと考える子供もいるでしょうから、フリースクールも存在意義はあると思います。どうも日本人の悪い癖で、型にはまらないものは悪いもの、と思ってしまう傾向があるように思います。ホームスクールやフリースクールで教育を受けたからと言って変に構えたりせず、社会の一員として認める必要があるように思います。ただ、問題は(特に日本では)これらの学校で教育を受けた子供がまだまだ少なく、成長してどのような大人になっているのか、社会にどのように貢献出来ているのか、どうも傾向がつかめないことだと思います。今の段階で、ホームスクールやフリースクールの意義は認めつつも、その是非を論じることは少し無理があるように思います。
先日、非常に興味深い記事を発見しました。AI(人口知能)の発達により、近未来的に社会に大きな変革が訪れる、というものです。自動車が運転しなくても目的地に連れて行ってくれたり、家に帰ったらまずロボットに「ただいま」と挨拶するような時代が、もうそこまで来ているのです。そして、今まで人間に与えられていた仕事の一部がAIで代替されるようになり、社会で必要とされる人材(スキル)も今までとは異なってくる。最終的に人材を育てる学校も変革せざるを得ないという結論になる、という訳です。こうして理論立てて説明されると、本当にその通りですね。例えば、会計士の仕事はAIで代替可能となった場合には、もはや会計士を育てる必要はなくなりますね。これから先、あまり遠くない未来に教育界にも大きな変化の波が押し寄せることが予想されます。教育に携わるものの一員として、これからも新しい動きに迅速に反応出来るように用意しておくことが大切だと思っています。
AICアクティング・エクゼクティブ・ディレクター 中村敬志
1970年、島根県生まれ。 13年間の地方銀行勤務を経て、広島県に本部を置く教育関連企業に転職。 2006年より、Auckland International College(AIC)に勤務。